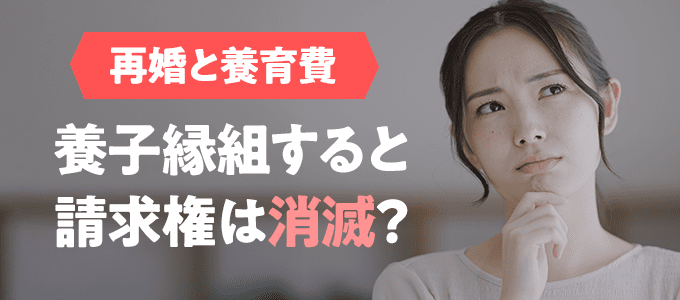
再婚したことで養育費を受け取る権利(請求権)を失わないために注意すべきポイントを整理しておきます。
再婚によって養育費にまつわる権利義務が変化するケースは限定的ですが、知らずにいると思わぬ形で請求権を失ってしまう可能性もゼロではありません。

注意点1: 連れ子の養子縁組は慎重に
養子縁組をすると養育費請求権(相手への請求権)は基本的に消滅すると考えましょう。
あなた(受け取る側)が再婚相手と子どもを養子縁組させた場合、元配偶者に対する養育費の請求は原則できなくなります。

もちろん、養子縁組には養育費以上に大きなメリットや事情があるかもしれません。
例えば新しい父親との間で法的親子関係を結ぶことで子どもに安定を与えたい、戸籍や姓を統一したい、養父からの相続権を得させたい等です。
その場合は元配偶者からの養育費は諦める覚悟を決める必要があります。
養育費以上に新しい家庭でのメリットが大きいと判断すれば、選択肢としてはあり得ます。

もし養子縁組をした後に状況が変わり、「やっぱり養育費がないと苦しい」となっても後の祭りです。
法律上は、養子縁組後でも元親(実親)は第二次的扶養義務者として完全にゼロではないのですが、実際に請求が認められるのは養親(再婚相手)が扶養できない特段の場合に限られます。

注意点2: 養育費減額に安易に同意しない
再婚を理由に元配偶者から養育費の減額提案をされるケースがあると述べました。
ここでの注意点は、安易に「じゃあ減額でいいです」と合意してしまわないことです。

よくあるのが、母親が再婚した際に元夫から「新しい家庭ができたならうちの負担を減らしてほしい」と言われ、情に流されて半額にしてしまうケースです。
しかし、新しい家庭の収入が安定しているとは限りませんし、新たな子どもが生まれたらむしろお金がかかるかもしれません。
また新しい夫に何かあれば、再び養育費が重要になる場面もありえます。
そのため、将来の見通しが不透明なうちは、養育費は減らさず現状維持とする方が安全です。
どうしても経済状況的に減額せざるを得ない場合でも、一時的な措置に留めたり、できれば調停などで客観的に妥当な額を決めてもらったりすると良いでしょう。
少なくとも、口約束やLINEのやり取りだけで減額に応じるのはリスクが高いです。

注意点3: 養育費受取りを自主的に止めない
こちら側の判断で養育費受け取りをストップしてしまうケースも見られます。
例えばシングルマザーが再婚する際に、「もううちは大丈夫だから」と元夫に伝えて支払いを打ち切らせてしまう、といった例です。

養育費はあくまで子どものためのお金なので、親であるあなたが「要りません」と言ってゼロにしてしまうのは、本来望ましいことではありません。
先方にとってはラッキーでしょうが、子どもにとっては損失です。
新しい家庭が裕福だったとしても、その養育費分を子どもの将来資金として貯蓄しておくことだってできます。

もし再婚相手やその家族から「もう前の配偶者からお金をもらう必要はないのでは?」と言われるようなことがあっても、「子どものために取り決め通り頂くことにしている」ときっぱり伝えましょう。
これは決して卑しいことではなく、子どもの利益を最優先しているだけなのです。
ただし例外として、元配偶者が経済的に非常に困窮している場合に「これ以上請求するのはかえって子どものためにもならない」と判断することはあるでしょう。
例えば元夫が病気や事故で働けず生活保護を受けている、といったケースです。
そのような場合は、請求しない(または一定期間猶予する)こともやむを得ないかもしれません。

注意点4: 再婚時に正式な合意を書面に残す
再婚にあたり、元配偶者との間で養育費に関する条件を改めて取り決め直す場合があります。
例えば「あなたが再婚するなら今まで面会を制限していたのを緩和する代わりに、養育費は減額してほしい」とか「養子縁組するので今後の養育費免除に同意してほしい」とか、様々な取り決めがありえます。

口約束で済ませると、後で「あれは言った/言わない」の争いになる危険があります。
公正証書が作れればベストですが、難しければ双方署名捺印の合意書でも構いません。
理想は第三者(弁護士や調停委員)を入れて合意内容を確認してもらうことです。
再婚という節目に過去の約束を見直す場合も多いと思いますが、その変更は子どもの生活に関わる重要事項です。
曖昧にせず、きちんと形に残しましょう。
特に、養育費受け取りを終了する(免除する)場合や大幅減額するような場合は、必ず公証人役場で公正証書にしましょう。
そうでないと、後に万一話が違ったと争う際に非常に不利になります。

注意点5: 新しい配偶者にも養育費の重要性を理解してもらう
これは請求権そのものの話ではありませんが、再婚相手にも養育費が子どもの権利であることを理解してもらうことは大事なポイントです。
万一、再婚相手が「前の旦那からお金をもらい続けるなんて嫌だ」などと言い出すと厄介です。
そのせいで、受け取りを辞退する羽目になってしまっては本末転倒なので、事前にしっかり話し合っておきましょう。

養育費についても、「子どものために元○○さんから頂くのは当然のことだよ」「将来の学費に充てたいから、私は受け取り続けるつもりだ」と伝えておきます。
それに対してネガティブな反応を示すようなら、改めて二人の価値観を議論する必要があります。
結婚後に揉めるより、前もってクリアにしておくべきです。
もし再婚相手の説得が難しい場合は、専門家の意見や統計データを見せるのも効果的です。
例えば「ひとり親家庭の貧困率は高く、養育費を受け取ることが子どもの生活安定に直結する」「国も養育費受取りを推進している」という話や、厚労省の調査結果などを見せても良いでしょう。
