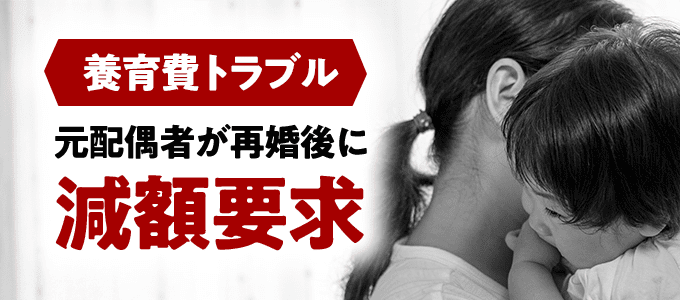
元配偶者が再婚した場合に養育費をきちんと支払ってもらうための交渉術について考えてみましょう。
離婚後しばらくは順調に養育費を受け取れていたのに、相手が再婚した途端に「減額したい」「支払いをやめたい」と言い出した…というケースは決して珍しくありません。

元夫・元妻が再婚した場合でも、勝手に養育費の支払いを止めることは認められません。
しかし実際問題として、相手側の家庭環境が変わると養育費についての姿勢も変わってしまう人がいるのも事実です。

相手の再婚によくある心理と状況変化を理解する
まず相手が再婚したことで何を感じ、どうして養育費支払いに消極的になるのかを考えてみましょう。

新しい家族への出費増
再婚相手との間に新たな子どもが生まれたり、再婚相手が専業主婦(主夫)だったりすると、元配偶者の家庭の出費が増えます。
その結果、「前の子どもに払うお金を減らしたい」という気持ちが出てくることがあります。

新しい配偶者からの影響
元配偶者の再婚相手(継父・継母)が養育費支払いに否定的な影響を与えるケースもあります。
例えば新しい妻が「前の奥さんにお金を渡すなんて嫌だ」と感情的に反対する場合や、新しい夫が「うちにも子どもがいるのに前の家庭にお金を払うのはおかしい」と言う場合です。
実際のYahoo!知恵袋でも、再婚した夫の新妻が「養育費を減らせないか」と口出ししたいような相談に対し、「養育費は子の父母間の取り決めでありあなた(新妻)は法的第三者なので口出しする権利はありません。旦那様の意思を尊重しましょう」という厳しい回答が寄せられていました。

「もう他人」意識の増大
元夫・元妻がお互い再婚すると、お互いの生活圏が完全に分かれるため心理的距離がさらに広がります。
「もう自分とは関係ない人だ」という意識が強くなり、養育費の重要性が薄れてしまう場合があります。
特に離婚後、子どもとの面会交流がほとんど無い父親の場合、新しい家庭に集中するあまり前の子どもへの関心が減少してしまう懸念があります。

以上のような背景を踏まえると、交渉の際には相手の再婚後の事情にも一定の理解を示しつつ、しかし子どもの権利は譲れないというスタンスで臨むのがコツです。

交渉術1: 子どもの必要と相手の愛情に訴える
再婚した元配偶者に養育費を払ってもらうためには、頭ごなしに義務を説くだけではうまくいかないことがあります。
特に相手に新しい家族ができている場合、「法律では払う義務があるでしょ!」と詰め寄ると防御的になってしまうかもしれません。
そこで効果的なのが、子どもの必要性と相手の子どもへの愛情に訴える方法です。

「娘は今小学○年生で、来年は修学旅行があります。
最近は物価も上がっていて何かとお金がかかるけれど、あなたにもらっている養育費で本当に助かっています。娘も感謝してます。」
「あなたが再婚して新しい家庭ができたこと、本当に良かったと思っています。
ただ、○○(子どもの名前)はあなたがお父さんであることに変わりなく、大事に思っています。
将来は〇〇の進学費用も必要になりますが、その時にも『お父さんが支えてくれたおかげだよ』と言えるようにしたいんです。」

実際、弁護士監修の記事でも「できるだけ有利に話し合いを進めるためには、元夫の子どもへの愛情に訴えかけていくべきです」とアドバイスされています。
相手が親としての良心や愛情を持っていれば、このアプローチは心に響く可能性があります。
もちろん、相手が全く非協力的で愛情も希薄なケースでは難しいかもしれません。
しかし試してみる価値はあります。

特に子どもに関することならなおさらでしょう。
交渉術2: 冷静な話し合いの場を設ける(第三者の活用も)
相手が再婚している場合、直接顔を合わせて話し合うのが難しいケースもあります。
新しい配偶者の手前、元妻と会いたがらない元夫もいるでしょう。

文章なら感情的になりにくく、こちらの言い分も整理して伝えられます。
また記録にも残るので、後々「言った言わない」の争いを防ぐメリットもあります。
それでも話し合いに応じてくれない、メールすら返事がないという場合には、家庭裁判所の調停を利用することを視野に入れましょう。
養育費の調停は再婚後でも問題なく申し立てできますし、調停委員という第三者が入ってくれるので当人同士より冷静な話し合いが期待できます。
例えば、「何度連絡しても返事をもらえないので、家庭裁判所で改めてお話し合いさせてください」というように伝え、正式な場に持ち込むのも一手です。

交渉が決裂しそうなときは…
弁護士に相談するのも有効な手段です。
「話し合いが膠着したら弁護士に相談してください」という助言が示すように、自分たちだけでは埒が明かない場合、法的代理人を立てることで状況が動くことがあります。
内容証明郵便で支払いを促す手紙を送ってもらったり、調停の申立てを代理で行ってもらったりすれば、相手も重く受け止めるでしょう。

交渉術3: 新しい配偶者とは直接やりとりしない
相手が再婚している場合、その新しい配偶者(継母・継父)の存在は交渉に影響を及ぼすことがあります。
しかし基本的なスタンスとして、新しい配偶者とは直接交渉しない方が得策です。

例えば元夫が再婚している場合、新しい奥さんに「あの…養育費のことで」と連絡をとったり、逆に奥さんの方から口を出されたりすると、感情的なもつれが生じやすくなります。
新しい奥さんからすれば、自分の家庭のお金が前妻に渡ることに複雑な気持ちを抱く場合もあるでしょう。
それを直接ぶつけられてしまうと、こちらも感情的になってしまうかもしれません。

もし新しい配偶者と直接会う機会があっても、養育費の細かい話題は避け、「うちの子がお世話になります」程度の挨拶に留めるのが無難です。
万一、新しい配偶者から養育費について文句や要望を言われた場合でも、「その件は元〇〇さん(あなたの元配偶者)と話し合って決めていますので」とかわし、深く議論しないようにします。
実体験のヒント
あるシングルマザーの方は、「元夫の再婚相手から電話で『うちも生活が厳しいので養育費を減らしてほしい』と言われ困惑した」という体験談をブログで紹介していました。
彼女はそこで感情的に反論せず、「では改めて〇〇さん(元夫)ときちんと話し合いたいと思います」とだけ伝えたそうです。
その後、元夫と直接調停で話し合い、結果的に養育費減額は却下されたとのことでした。
このケースからも、新しい配偶者との直接やりとりは避け、公式の場で当事者同士が話すことが重要だと分かります。
交渉術4: 支払い状況の記録と証拠を確保する
養育費の交渉を有利に進めるために、これまでの支払い状況を記録し証拠を揃えておくことも有効です。

養育費の受取証拠
銀行振込であれば通帳記帳やネットバンキングの明細を保存。
手渡しの場合は領収書を書いてもらうか、受け取った日にメモしておく。
これまでの滞納状況
もし過去に何度か未払い・遅れがあったなら、その日付と金額を一覧に。
メールで催促した履歴なども残しておく。
養育費合意の証拠
離婚時の公正証書や調停調書があればコピーを用意。
口約束しかない場合でも、当時やりとりしたLINEやメールがあればスクショを印刷。
これらを整理しておけば、いざ相手が「払ってないなんてウソだろ?」などと言ってもすぐ反証できますし、「これだけ滞っている」という事実を突きつけることもできます。
交渉の場では感情論ではなく数字と記録で淡々と話す方が相手も冷静になりやすいです。
また、記録がしっかりしていれば最悪交渉が決裂して法的措置に移る際もスムーズです。
「いざとなれば法的手段もある」という姿勢を見せること自体が交渉力になります。

交渉術5: 減額提案には安易に同意しない
元配偶者が再婚後に「うちも子どもができたから、養育費を○万円に減らしてもらえないか」と持ちかけてくることがあります。
このような減額交渉に対しては、安易に同意しないことが重要です。
相手の事情も分からなくはないと思って譲歩したら、後になって「あの時やっぱり同意しなければよかった」と後悔するケースも多いからです。
一度減額に合意してしまうと、基本的にはそれが新たな取り決めとなってしまいます。
(公正証書を作り直した場合などは特に)

ですから、減額提案には慎重に対応する必要があります。
相手の言い分を聞く
なぜ減額したいのか具体的に尋ねます。
本当に収入が減ったのか、新家庭でどれだけ出費が増えたのかを確認しましょう。
単に「再婚したから」という理由だけなら法律上認められにくいことを冷静に伝えても良いです。
子どもの必要を伝える
減額に応じると子どもの生活や教育にどんな影響が出るかを説明します。
「現在の養育費○万円でも塾代や学費で精一杯で、これ以上減ったら習い事をやめさせないといけなくなる」など具体的に伝えます。
話し合いで結論を急がない
その場で「わかりました」と言う必要は全くありません。
「持ち帰って考えさせてください」と言って一旦保留にしましょう。
これは心理的駆け引きの面でも有効です。
相手としては減額に同意してもらえるか不安になりますから、こちらに有利な条件を出してくるかもしれません。
調停での客観判断を提案
どうしても折り合わない場合は、「この件は家庭裁判所で判断してもらいましょうか」と提案するのも手です。
専門家に委ねる姿勢を見せることで、相手もむやみに無茶な要求はできなくなります。
兵庫県弁護士会のQ&Aでも「元夫から再婚を理由に養育費減額の申し入れがあったが、直ちに応じる義務はない」と回答されています。
むしろ、相手が調停を申し立てて正式に減額が認められるまでは、従来通りの金額を請求し続けることができます。

不公平な要求には毅然と対処しましょう。