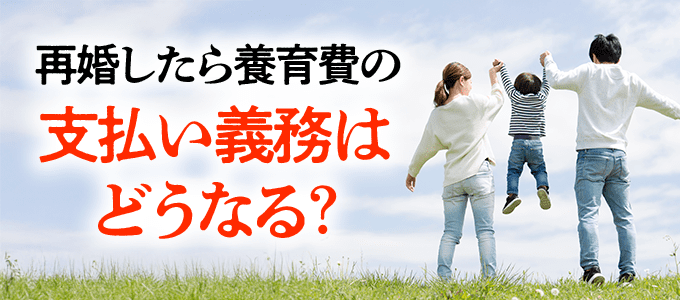
再婚しても親の扶養義務は基本的に継続
まず押さえておきたい基本原則は、親は離婚後も子どもを扶養する義務を負うということです。
たとえ父母のどちらか、または双方が再婚した場合でも、それだけで自動的に養育費の支払い義務が消滅するわけではありません。
日本の民法上、親子である以上は生活保持義務(自分と同程度の生活を子に保障する義務)があり、離婚や再婚によって親子関係が断たれない限り(特別な養子縁組を除き)、この義務は原則として続きます。

例えば、JA埼玉の法律相談でも「将来、あなたが再婚しても、元夫に養育費を請求することができます」と明言されています。
再婚相手は子どもと法律上の親子ではない限り扶養義務を負わないため、再婚後も実の親同士で養育費を分担し続けることになるわけです。
ポイント
離婚して親権者である母が再婚した場合でも、元父は法律上引き続き子に対する扶養義務(生活保持義務)を負います。
再婚相手(継父)には法的扶養義務がないため、母の再婚のみを理由に父が一方的に養育費を打ち切ることは許されません。
養子縁組した場合は例外あり – 再婚相手が「法律上の親」になるケース
再婚によって基本的な扶養義務は変わりませんが、一つ大きな例外となるのが養子縁組です。
具体的には、子どもが再婚相手と養子縁組(いわゆる「連れ子養子縁組」)をした場合、法律上その再婚相手が新たな養親となり、実親である元配偶者は扶養義務者としては第二順位に後退します。

厚生労働省の「ひとり親家庭支援の手引き」にも、「事実上子どもが再婚相手にも扶養されているなどの事情によっては、養育費の減額が考慮される要素になる可能性がある」と記されています。

例えば、離婚専門の弁護士による解説でも「再婚相手と子どもが養子縁組している場合は、養育費は支払わなくてOKになる」と明言されています。
実際にYahoo!知恵袋でも「元嫁が再婚したら子供の養育費払わなくて良いんですか?」との質問に対し、「必ずしも再婚したからといって免除されるとは限らないが、再婚相手と子どもが養子縁組した場合は養育費支払い不要になる」という趣旨の回答が寄せられていました。
ポイント
再婚相手と子どもが養子縁組をすると、再婚相手が子の第一義的扶養義務者となります。
これにより元の親(実親)は扶養義務が法律上二次的な立場となり、基本的には元親からの養育費請求はできなくなります。
養子縁組をした時点で、元親の養育費支払い義務は免除されると考えて良いでしょう。
もっとも、養親となった再婚相手に十分な扶養能力がない場合には例外的に請求可能性が残る余地はあります。
注意
養子縁組によって養育費の権利義務関係が変わる点は非常に重要です。
養子縁組をするかどうかは、新しい家族関係をどう築きたいかだけでなく、経済的・法律的な影響も踏まえて慎重に判断する必要があります。
養育費の金額調整:再婚による「事情の変更」とは?
再婚そのものでは養育費の支払い義務は消えませんが、養育費の金額を見直す要因にはなり得ます。
法律上、いったん決めた養育費の額でも、その後の事情変更があれば家庭裁判所に請求して増額・減額をすることが可能です。

受け取る側(監護親)が再婚した場合
再婚相手が子どもと養子縁組していない限り、前述のとおり元配偶者(実親)の扶養義務に変わりはありません。
従って、基本的に養育費の金額も変更されないのが原則です。
再婚相手の収入が高く「もう十分だろう」と思われるケースでも、法律上その収入は考慮されません。

具体的には、養育費支払い中の父親が「子どもは母の再婚相手にも養われているのだから、自分の負担を減らしたい」と家庭裁判所に調停を申し立てるケースです。
この場合、子どもの生活状況や再婚相手の扶養状況などを総合考慮し、養育費が一定程度減額される可能性はあります。

支払う側(非監護親)が再婚した場合
父(母)が再婚しただけでは、やはり子どもとの法律上の親子関係は変わりませんので養育費支払い義務は継続します。
ただしこちらも「事情の変更」として養育費の減額を求める余地が生じます。
典型的なのは、再婚相手との間に新たな子ども(異父兄弟・異母兄弟)が生まれた場合です。

実際、兵庫県弁護士会の法律相談でも「元夫が再婚して新家庭を持ったので養育費を減額したいと言われたが、応じるべきか?」という質問が紹介されています。
それによると、元夫の再婚は「扶養家族の増加」に当たり事情変更と認められるため、調停などである程度の減額が認められる可能性があるとのことです。
特に元夫に新たな子どもができて生活費の負担が増えた場合、裁判所が養育費算定表の計算上で元夫の生活費指数を上げて調整することが考えられます。

参考
家庭裁判所は民法880条に基づき「事情に変更」があれば養育費の額を変更できます。
再婚による扶養家族の変化(新しい子の誕生など)は典型例ですが、調停での判断はケースバイケースです。
例えば「再婚は想定内で合意していた」「収入が大幅増減した」など事情によって結論は異なります。
減額が認められる場合も、申し立てをした時点以降の支払いについて適用され、過去に遡って免除されることは通常ありません。
安易に相手の口約束に応じてしまわず、正式な手続きを踏むことが大切です。
親権や面会交流との関係
ここで少し補足ですが、養育費の支払い義務は親権の有無や面会交流の実施状況と無関係です。

時々「面会もさせてもらえないのに養育費を払うのはおかしい」といった声を耳にしますが、法的には養育費と面会交流は別問題として扱われます。
極端な話、親権者が再婚して子どもとの新生活を始め、前の配偶者との接触を絶っていたとしても、それだけで養育費の免除は認められません。
「会わせてもらえないなら払わない」という自己判断はトラブルのもとですので避けましょう。
逆に、養育費をきちんと払っているからといって親権が復活したり優先されたりすることもありません。
