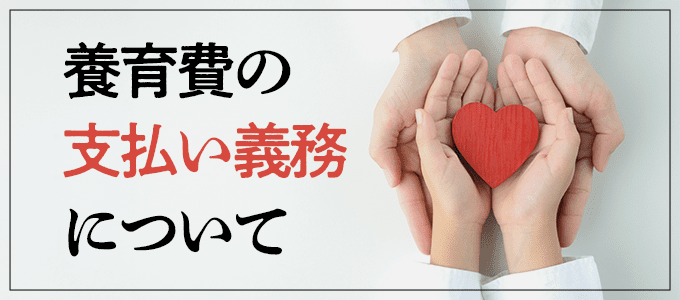
離婚や別居後に子どもを育てていく上で必要なお金、それが「養育費」です。
養育費とは、一言でいえば子どもの健やかな成長に必要な生活費のことです。

たとえ両親が離婚して別々の生活を送るようになっても、親であることに変わりはありません。
法律上、親は未成熟の子を扶養する義務(扶養義務)を負っており、その関係は離婚後も続きます。

養育費の基本的な仕組みとしては、通常、親権者でない方の親(非監護親・別居親)が、子どもを引き取って育てている親(監護親・同居親)に対して支払います。
支払い方法は毎月一定額を銀行振込などで渡す場合が多く、金額は子どもの人数や年齢、そして双方の収入に応じて決められます。
養育費は子どもの権利でもあります。
養育費を受け取る親にとっては元配偶者からの援助という側面がありますが、元を正せばそれは子どものためのお金です。

法律の定義や根拠についても触れておきます。
日本の民法第877条では直系血族(親子や祖父母と孫など)間の扶養義務が定められており、親は子を扶養する義務があります。
また、2011年の民法改正で第766条に離婚時の取り決め事項として「子の監護に関する事項(親権者や養育費、面会交流など)」が明文化されました。
これにより離婚届を提出する際にも本来は子どもの養育費についてしっかり取り決めることが望ましいとされています。
もっとも、離婚届け自体には養育費の合意が要件とはなっておらず、取り決めがなく離婚成立してしまうことも多いのが実情です。

なお、養育費というと離婚した夫婦の間の話と思われがちですが、正式に婚姻していなかった場合(未婚のシングルマザー・ファザー)でも状況は同じです。
父母が婚姻関係になくとも、父親が認知している子であれば父親に扶養義務がありますので、母親は父親に対して養育費を請求できます。
「籍を入れていないから養育費は関係ない」と思われるかもしれませんが、子どもにとって実の親であることに変わりはありませんので、請求や取り決めは可能です。

厚生労働省の調査によれば、離婚後に元配偶者から現在も養育費を受け取っている母子家庭の母はわずか24.3%にとどまります。
過去に受け取ったことがある人(途中で途切れてしまったケース)が15.5%、「一度も受け取ったことがない」が56.0%というデータです。
つまり、半数以上のシングルマザーが養育費を全く受け取れていない現実があります。
このように日本の養育費不払い問題は深刻ですが、近年ようやく国も重い腰を上げ、2031年までに養育費受け取り率を40%に引き上げる目標を設定するといった動きも出てきました。
