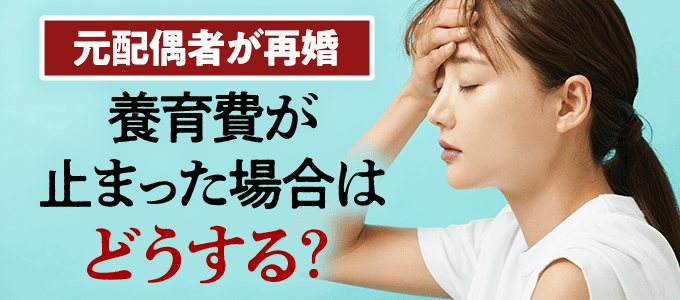
残念ながら、養育費を支払ってくれない元配偶者も多く存在します。
厚生労働省の調査では、離婚母子世帯で実際に養育費を受け取っている割合は2~3割程度という結果もあります。
では、養育費を払っていない(滞納している)相手が再婚した場合、どのように対処すればよいでしょうか。
状況としては、「離婚後一度も払ってもらっていないのに相手が再婚してしまった」「途中までは払っていたのに再婚を機に払わなくなった」といったケースが考えられます。

まずは状況を整理 – 再婚は関係なく支払い義務は残っている
大前提として、相手が再婚しようと支払い義務は消えていません。
(養子縁組がされていない限り)
ですから、「再婚したからもう取れない」と悲観するのは禁物です。
むしろ再婚したことで相手の生活が安定した可能性もあります。
例えば新しい配偶者が働いて二馬力収入になっているとか、家庭を持つことで定職に就いたとか、プラスの変化も考えられます。

- 養育費の取り決め状況: 公正証書や調停調書があるか。それとも口約束だったか。
- 滞納の期間と金額: 何年何月から支払われていないのか。累計でいくらになるのか。
- 相手の再婚情報: 再婚相手はどんな人か(職業・収入など可能な範囲で把握)。相手に新しい子どもがいるか。相手の住所や勤務先は分かるか。

特に債務名義(公正証書や判決など)があるかないかで対応が変わります。
ケース1: 債務名義がある場合(公正証書・調停調書など)
既に養育費について公正証書を作成済み、または調停・審判で決定済みの場合は、法的執行手段を躊躇なく使いましょう。

履行勧告を申し立てる(任意)
まず穏便に済ませたい場合、家庭裁判所に「履行勧告」を申し出ます。
これは、家庭裁判所から相手に「養育費を支払いなさい」という督促状を送ってもらう制度です。
費用は無料で、相手に心理的圧力をかける効果があります。

強制執行の準備
相手がそれでも払わない場合、地方裁判所で強制執行手続きを行います。
必要なものは債務名義(公正証書正本など)と相手の財産情報です。
最も確実なのは給与差し押さえでしょう。
相手の勤務先が分かれば、給与を差し押さえて未払い養育費に充当できます。

月々の給与の1/2まで差し押さえ可能です。
財産調査
勤務先が不明・無職の場合は、預金口座や自動車、不動産などを調査します。
弁護士に依頼すれば職権で預貯金を調べられる場合もありますし、裁判所に「財産開示手続」を申し立てて相手を呼び出し、資産を申告させる制度もあります。
(相手が無視すると罰則あり)

差し押さえ実行
相手の財産が判明したら、差押命令を出してもらいます。
例えば銀行口座ならその口座のある支店宛に執行官が差押命令を送達し、未払い分に達するまでの預金を凍結・回収します。

ただし費用がかかるので、未払い額との兼ね合いになります。
近年、一部自治体では養育費回収のための弁護士費用を補助しているところもあります。
例えば横浜市などでそうした事業が報告されています。

再婚の影響
相手が再婚したこと自体は、あなたが強制執行する上でほとんど障害になりません。
むしろ上記のように財産が増えている可能性もあるので追い風です。
注意すべきは、相手が資産を新しい配偶者名義に変えてしまうケースですが、給与は本人名義ですし、預金も生活に使う以上全部配偶者名義というのは非現実的です。

ケース2: 債務名義がない場合(取り決め自体していないor公正証書等なし)
離婚時に養育費の取り決めをしていなかった、または文書に残していなかった場合、まず債務名義を得ることが先決です。

家庭裁判所に調停を申し立てる
養育費請求調停を起こします。
相手の住所地の家庭裁判所が通常管轄です。
相手に調停の呼出状が届きます。

調停で未払い分も含め協議
本来離婚時から現在まで支払われていないのであれば、遡及分を請求できるかが争点になります。
養育費は通常、請求した時点から認められることが多く、過去分は「事情による」とされます。
ただ調停委員に事情を説明し、相手に支払い能力がある程度あるなら、ある程度の遡及分(例えば調停申立ての数ヶ月前からなど)をまとめて払うよう求めてくれるかもしれません。

不調なら審判へ
相手が調停に出てこなかったり合意しなかった場合、審判手続に移行します。
裁判官が双方の事情を踏まえて養育費額を決定し、審判書が送られてきます。
これも債務名義になります。
こうして債務名義を得たら、先ほどのケース1と同じく強制執行が可能です。
相手が再婚して連絡を避けていたようなケースでも、調停の呼び出し状は公的に届きますので、相手も無視しづらくなります。

ケース3: 相手と直接話し合える場合 – 新配偶者を巻き込まない工夫
滞納相手が再婚していても、なお直接話し合える関係性が残っている場合は、再婚相手を巻き込まず二人で解決するのもありです。
お互い再婚している状況なら、尚更当人同士で落とし所を見つけた方がシンプルでしょう。

その代わり今後の額は減額に応じる」といった交渉も一つです。
相手としては、新しい家庭に毎月払い続ける額が減るなら、滞納分の一部を分割で払う方が得かもしれません。
お金の総額と支払いスケジュールで譲歩案を提示し、合意できれば公正証書に残すのがおすすめです。
ただし、直接交渉は感情的トラブルに発展するリスクもあります。
少しでも難しければすぐ調停等に切り替えましょう。
「元夫が再婚相手と一緒に乗り込んできて話し合いが修羅場に…」なんてことになると本末転倒です。

新しい配偶者へのアプローチは慎重に
養育費を払わないまま再婚した相手に対し、「新しい奥さん(旦那さん)にチクってやろうか」と考える人もいるかもしれません。
確かに、新配偶者が滞納の事実を知れば、相手に支払いを促してくれる可能性もあります。

下手をすると「非常識な前妻(前夫)だ」と新配偶者から反感を買い、状況がこじれる恐れもあります。
ですから、新配偶者への直接アプローチは最終手段と考えましょう。
それよりは上記の法的手段を粛々と進め、結果的に新配偶者の耳にも入る…という形が望ましいです。
例えば給与差し押さえになれば、その職場や家族には知られますし、調停に呼び出されたら新配偶者にも事情を説明せざるを得ないでしょう。
例外的なケース
もし新配偶者があなたの知人であったり連絡が取れる間柄で、かつ常識的な人であれば、「実は○○さん(元配偶者)から養育費が未払いで困っている」と相談してみるのもゼロではありません。
新配偶者にとっても後でトラブルになるより先に対処しておきたいと思うかもしれません。
ただ、この場合も相手のプライドを傷つけないよう配慮し、「あなたを責めるつもりはないけど…」と丁重に伝える必要があります。

「取れない」と思い込まず専門家に相談を
養育費の未払い案件は状況が複雑なことも多いです。
相手が自営業で収入を隠している、行方不明気味、再婚相手と海外移住した等、困難パターンもあり得ます。

意外な解決策が見つかるかもしれません。
最近は国も養育費確保に力を入れており、養育費のための法的支援を自治体でモデル事業として行う例もあります。
例えば「弁護士費用補助」「データベースで所在調査」など、新しい施策が試行されています。
また、弁護士による「養育費相談は着手金無料・成功報酬型」というプランを掲げる法律事務所も出てきています。

【まとめ】養育費を払わない相手が再婚しても、取れる手段はたくさんあります。
肝心なのは諦めずに行動することです。
法的措置を講じることでしか得られない結果も多々あります。
再婚したことで逆に相手の居場所がはっきりしたり、収入が安定したりするケースもあるので、悲観せず戦略的に進めましょう。
